電通デジタルの広告領域を牽引するエース集団「営業戦略部」とは?

電通デジタルの中核を担うマーケティングコミュニケーション(以下MC)領域は、1,000名を超えるメンバーを擁しています。その巨大組織を支えるべく2024年に営業戦略部が誕生しました。エース級の人員で組織された営業ヘッドクォーターとしてMC領域を牽引する営業戦略部とは、どのような組織なのでしょうか? 部長の岡田健太郎とディレクターの一宮慎治に聞きました。
目次
- 広告を中心に、クライアント企業のマーケティング課題を解決するMC領域
- より深い専門性とスピード感で、きめ細やかな対応を行うために発足
- 営業戦略部の3つの機能とは
- 全員が現場プレイヤーのミドルオフィスだからできること
- より大きな課題へ取り組み、クライアント企業からも認知される組織へ
広告を中心に、クライアント企業のマーケティング課題を解決するMC領域
――MC領域のカバー業務と役割を教えてください。
岡田:一般的にMCは広告領域を指しますが、電通デジタルでは、クライアントに対して、メディアに閉じない提案をおこなっています。
一宮:MC領域は、クライアントのマーケティング課題を解決するための組織として、広くデジタルマーケティング全般を支援しています。電通デジタルが持つアセットの中から、もっとも適切なソリューションを提案するということが根幹にあります。
より深い専門性とスピード感で、きめ細やかな対応を行うために発足
――営業戦略部が発足した背景をお聞かせください。
岡田:MC領域には、以前から横軸組織として営業企画部がありました。営業戦略部の前身です。営業企画部は売上や生産性向上の糸口を発掘し、解決策を企画・立案・実行することを目的に、1つの事業部として稼働していました。2024年に入り、より深い専門性とスピード感を持って、さらにきめ細やかなクライアント企業対応を行うために、新たに営業戦略部として発足しました。
一宮:営業戦略部には、「営業推進グループ/営業企画グループ」と、「人事計画グループ」の2つの組織があります。
前者は、クライアント企業の課題解決の役に立つアセットを企画・開発することが目的。後者は、MC領域が組織横断の団体戦を行えるような組織になることが目的です。
――営業戦略部にはどのようなメンバーが在籍していますか?
岡田:アカウントプランナーを中心に、ストラテジックプランナー、プロジェクトマネージャー、現場マネージャーなど、主務の事業部門においてエース級の人財ばかりで構成されています。
たとえば、史上最年少マネージャーや史上最年少部長のほか、会社やプラットフォーマーのコンテストのMVP受賞者、社外の研修で講師を務める⼈材開発プランナーなど、MC領域を代表する人財が揃っています。
また、人事計画グループには人材開発プランナーという肩書きを持つ者が所属していますが、専門職としてミドルオフィサーが所属していることも、営業戦略部の特徴だと思います。
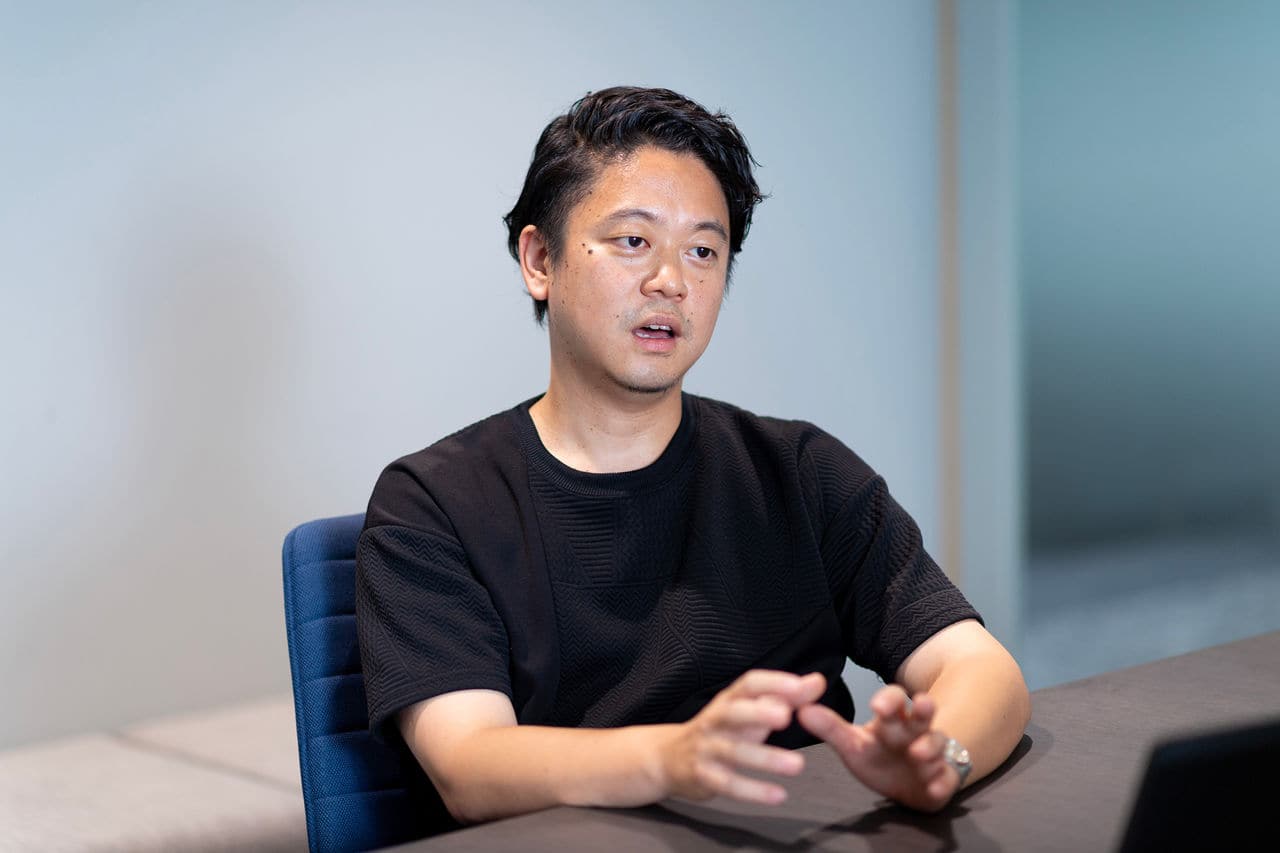
営業戦略部の3つの機能とは
――営業戦略部の主な機能について教えてください。
一宮:大きく3つの機能があります。
1つ目は、営業戦略機能。クライアント企業への価値提供を最大化するために、どのような戦略で、どう人を動かして、どのようなサービスを企画立案していくか、MC領域のヘッドクォーターとしての機能です。
2つ目は、研究開発機能。電通デジタルが常に最先端でいるために、未来を予測して、新しいことを切り開く機能です。1つ目の営業戦略で立案したサービスを電通グループ内のアセットを活用して具現化していき、他社との競争力を生み出します。
3つ目は、経営企画機能。経営視点から状況を把握し、それに対して打ち手を考え、最適な状態へ改善していく機能です。
岡田:1つ目の営業戦略機能は、営業戦略部の本丸になりますが、中でも競合提案のための情報支援は大きな役割の1つです。事前に社内にどういうアセットがあるか、どういう順序で進めていくとより競合企業に勝ちやすいかといった情報を提供するほか、アサインからチーミング、分析に関するサポートまで行うことで、事業部がより提案に集中できるようサポートします。
2つ目の研究開発機能は、クライアント企業のために市場調査を行ったり、広報戦略を考え、実行しています。それ以外の取り組みとして、「ナレッジレボリューション」と呼んでいる社内活動があります。各部署内でサイロ化したナレッジを社内に流通させて、現場のメンバーが必要な情報を簡単に引き出せるような仕組みを整備する取り組みです。ナレッジが社内に停滞する状況はクライアント企業のデメリットにもつながるので、その解消は重要な課題と認識しています。
具体的には、有志で運営されていた「KNOWLEDGE4」という毎週開催しているナレッジ共有の場を管理・運営するようになりました。フォーマットを定型化する、使用ツールを統一するなど、点在するナレッジを民主化していく作業は、フロント経験の豊富な我々だからこそできる作業でもあります。
一宮:ナレッジの管理には、クライアント企業の守秘義務を遵守しなくてはなりません。その点は厳格にルールを定めて運用しています。抽象化されたナレッジは、電通デジタルの全クライアント企業により高いクオリティのソリューションを提供するエンジンになると我々は考えており、最終的にはクライアント企業のためになるという考えで取り組んでいます。

全員が現場プレイヤーのミドルオフィスだからできること
――営業戦略部の強みは何ですか?
岡田:1つ目は、全員が兼務の人財だということです。これがミドルオフィスとしての活動に良い影響を与えています。一般的には、ミドルオフィスからの提案は現場と乖離したものが多くなりがちですが、我々の場合、現場で自分たちが、クライアント企業、プラットフォーマー、ツールベンダーと相対している課題をそのまま定義して企画実行できる点は、大きな特徴だと思います。
また、営業戦略部には、アカウントプランニング部門以外のさまざまな部門からメンバーが集まっています。彼らは、自分の専門性を活かすだけでなく、主務の部署で求められている機能を営業戦略部で実現しているという側面もあります。そうしたサイクルが営業戦略部の活力を高めていると捉えています。
2つ目に、意思決定スピードが早いこと。会社組織というのは基本的にはツリー型の意思決定構造ですが、我々はプロジェクトの実行責任と意思決定を、担当メンバーに権限委譲して、PDCAのスピードを速めています。これによって、少人数でも多くのプロジェクトが回すことができるのは大きな強みです。
一宮:3つ目の強みとして、私は構想力を挙げます。通常、チームで業務を行う際には、「SOW(Statement Of Work/作業範囲記述書)はここまで」「前提情報はこれ」「NG項目はこれ」といった前提条件の整備に時間がかかりますが、営業戦略部だとそうした事前作業はほぼ必要ありません。メンバー全員が構想力を持っているからです。
情報も、経験も、アイデアも持っているから、短時間の議論でも構想を具体化できるし、構想を自分の得意領域に引き寄せて持ち帰ることができる。その、0→1を、現場発でできるところが、営業戦略部の強さです。
主務でさまざまな課題に取り組んでいるエース級の人財が、営業戦略部という舞台で、電通デジタルをエンジンとして引っ張っていく。そのような強い志を持って取り組んでいるからこそ、構想力と実行力が十全に発揮されると認識しています。こうした現場感のあるミドルオフィスは稀有ではないでしょうか。
より大きな課題へ取り組み、クライアント企業からも認知される組織へ
――今後の展望をお聞かせください。
岡田:営業戦略部はMC領域の課題を見つけて解決するために生まれた組織なので、今後はもっと大きな課題の解決力を上げていきたいです。大きな課題というのは非常に抽象度が高いものです。メンバー1人ひとりが日々クリティカルに課題を設定し、それを解決する知識やスキルを磨いていく。それによって、大きな課題に対しても全員で立ち向かい、乗り越えていけるような組織にしていきたいと考えています。それがクライアント企業の課題解決にもつながっていくはずだと信じています。
同時に、クライアント企業に存在を認知され、高い評価を得られる組織になりたいなという野望もあります。競合提案支援のほか、普段の提案を充実させていくことで、「電通デジタルの営業戦略部ってすばらしい組織ですね」と言っていただけるような組織運営を行っていきたいです。